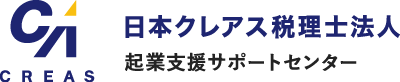年末調整の流れとポイント
こんにちは!創業サポートオフィスです。年末調整について調べていると、制度の仕組みや手続きの流れが複雑で悩む方も多いのではないでしょうか。この記事では、年末調整の基本的な仕組みから具体的な流れ、よくある質問や注意点までを徹底的に解説します。この記事を読むことで、年末調整に関する疑問が解消され、実務に役立つ正しい知識が身につきます。特に会社を経営されている経営者の方や、家族経営をされている方はぜひ最後まで読んでみてください!
年末調整とは何か
年末調整とは、給与所得者の1年間の所得税を正しく計算し、源泉徴収された税額との差額を精算する手続きです。会社が従業員に代わって行うため、個人で確定申告をする必要がない場合も多いです。実際には、扶養控除や生命保険料控除などを反映させ、正しい税額を確定させる重要な仕組みです。
年末調整が必要となる理由
給与から天引きされる所得税は毎月の見込み額に基づくため、実際の所得税額と一致しないことが多いです。年末調整によって、過不足が精算され、払いすぎた税金は還付され、不足分は追加で徴収されます。
年末調整を受けられる人の範囲
原則として給与所得者で、かつ会社に勤務している人が対象です。また退職後、再就職をしていない人も年末調整の対象となります。ただし、給与収入が2,000万円を超える人や、副業で確定申告が必要な人は対象外となります。
年末調整の流れと必要書類
年末調整の手続きは毎年11月から12月にかけて行われます。従業員は会社から配布される各種申告書に必要事項を記入し、控除証明書などの添付書類を提出します。その後、会社が源泉徴収票を発行し、翌年の確定申告に利用できるようになります。
従業員が準備する書類
扶養控除申告書、保険料控除申告書、住宅ローン控除関連の書類などが必要です。これらの提出が遅れると正しく控除が反映されないため、期限を守ることが重要です。
会社が行う手続きの流れ
会社は従業員から提出された書類を確認し、源泉徴収簿を基に再計算を行います。その後、12月の給与で精算を行い、翌年1月には税務署と従業員に対して源泉徴収票を交付します。
年末調整でよくある疑問
年末調整に関しては、毎年多くの従業員や経営者から質問が寄せられます。代表的な疑問点を取り上げ、詳しく説明します。
住宅ローン控除はどうなるか
住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で適用可能です。会社に提出する『住宅借入金等特別控除申告書』と金融機関発行の残高証明書を用意する必要があります。
副業をしている場合はどうなるか
副業で20万円以上の所得がある場合は、年末調整だけでは完結せず、確定申告が必要です。本業の給与は年末調整で精算されますが、副業収入は確定申告で申告しなければなりません。
途中入社や退職した場合の年末調整
その年の途中で入社した場合、前職の源泉徴収票を提出することで年末調整が可能です。一方、退職して再就職しなかった場合は、本人が確定申告を行う必要があります。
年末調整の注意点
年末調整は制度の理解不足から誤解やミスが起こりやすい分野です。経営者や担当者は、特に以下の点に注意する必要があります。
控除証明書の提出漏れ
生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を紛失するケースは少なくありません。証明書がないと控除が適用されないため、再発行を依頼することが大切です。
扶養の範囲に関する誤解
扶養家族の範囲について誤解が多く見られます。例えば、アルバイトをしている子どもが一定の所得を超えると扶養控除の対象外になります。正しい基準を理解することが重要です。
提出期限を守らないリスク
年末調整の書類提出が遅れると、従業員自身で確定申告を行う必要がでてきます。特に経営者は全従業員の提出状況を管理することが求められます。
まとめ
この記事では、年末調整の仕組みや流れ、よくある疑問や注意点について解説しました。年末調整は給与所得者にとって欠かせない重要な制度であり、正しく理解することで税負担を最適化できます。
創業サポートオフィスでは、会社設立サービスはもちろんのこと、創業融資等の資金調達(銀行融資)から、クラウド会計を活用した効率的な経理及び税務会計、法人決算、労務手続きまで幅広く対応いたしますので、煩雑な業務を安心してお任せください。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
監修 税理士 大谷 響